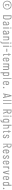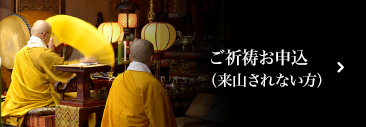行事
- 年中行事
- その他行事

秘仏特別御開帳 馬頭観音 三月・十一面観音 十月〜十一月

修正会(大般若会)一月一日~三日
除夜の鐘の響きとともに、本堂では大般若会が修されて、松三宝昆布挟みの儀が執りおこなわれ、護摩堂では越年の護摩が焚かれます。また境内には108本の竹明かりが灯されて、新年が言祝がれます。
三が日は大般若会の祈祷が終日続けられます。

光仁会 癌封じ笹酒祭り一月二十三日
桓武天皇が文武百官を伴い、先帝光仁天皇の一周忌の齋会を大安寺で営まれたという『続日本紀』の故事により、毎年一月二十三日に光仁会が行われます。
この法会は風雅な青竹づくしの祭儀で光仁天皇ゆかりの、「笹酒」の接待が行われます。「がん封じの笹酒」として、広く知られています。

節分会(開運星祭り)二月三日
開運星祭り。午後2時より、護摩堂にて開運厄除け祈願の星供護摩が焚かれます。
また、星供護摩終了後の午後3時頃より、本堂南側広場にて鬼追難会ならびに福豆まきが盛大に行われます。

馬頭観音厄除け法要三月午の日
大安寺の馬頭観音は、日本最古の像といわれ、その霊験は広く伝えられていますが、八代将軍吉宗の父紀州徳川二代藩主徳川光貞がことのほか信仰し、その霊験を秘文四字に浄書し、吉宗またその秘文を災厄除けの護符として幕閣・諸侯に頒ったということです。
二の午祭りでは護摩が焚かれ、災厄除けの「秘文神符」が授与されます。近年は馬主をはじめとした競馬関係者も、馬の安全加護を求めて参詣されます。
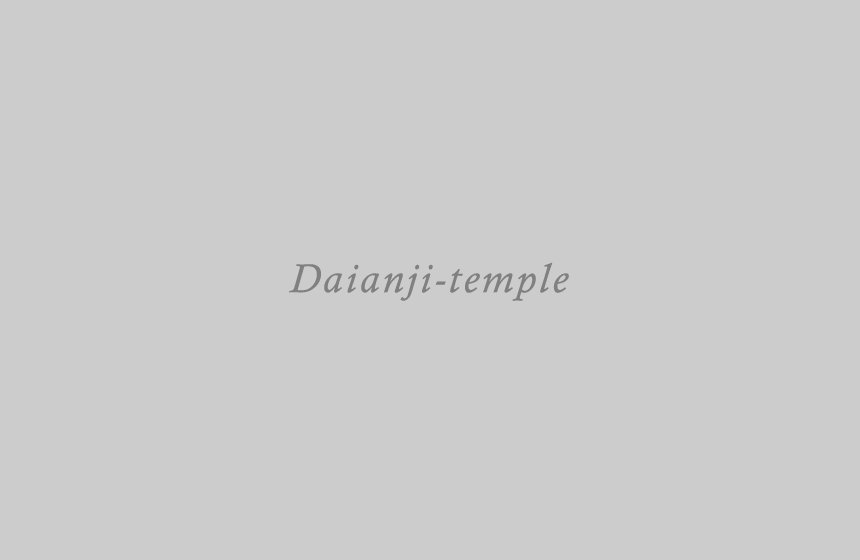
春彼岸会三月彼岸七日間

花まつり四月八日
お釈迦様のご生誕を寿ぎ、小さな釈迦像に甘茶をかけてお祝いします。

正御影供(弘法大師)四月二十一日
毎年旧暦三月二十一日の弘法大師の御入定日に、大師の御影を祀って供養する法会が正御影供(しょうみえく)であり、今日では新暦の四月二十一日に営まれます。
大安寺ではまず、大師の御影に供物を供え、午後一時から勤行式、続いて柴灯大護摩の修法が行われ、本堂を一回りするように、四国八十八ヵ所とインド八聖地のお砂踏みの行事が行われます。

勤操忌五月七日
奈良時代末期、大安寺の別当をされ、また弘法大師の師ともいわれている勤操大徳の御忌法要。
当日は、勤操大徳の御影をまつり大徳の高徳を偲ぶ。

青葉祭(弘法大師誕生法要)六月十五日
弘法大師のご誕生を寿ぎ、報恩謝徳の祈りを捧げる法要。人間国宝、鹿児島寿蔵氏が高野紙で作った稚児大師像をまつり、可愛い大師像に甘茶をかけて誕生を祝います。

竹供養 癌封じ笹酒夏祭り六月二十三日
古来中国では、陰暦五月十三日(六月二十三日ごろ)を竹酔日あるいは竹迷日、竜生日、竹誕日、竹供養と称し、この日に竹を植えればよく育つといわれています。
大安寺では、竹酔日の故事にちなみ、六月二十三日に「竹供養 癌封じ笹酒夏祭り」が行われています。終日笹酒の振る舞いや癌封じ祈祷が行われます。

お盆聖霊会八月一日~十五日
期間中、諸大寺の高僧や著名人の染筆の灯篭を掲げ、お盆施餓鬼供養会を行います。
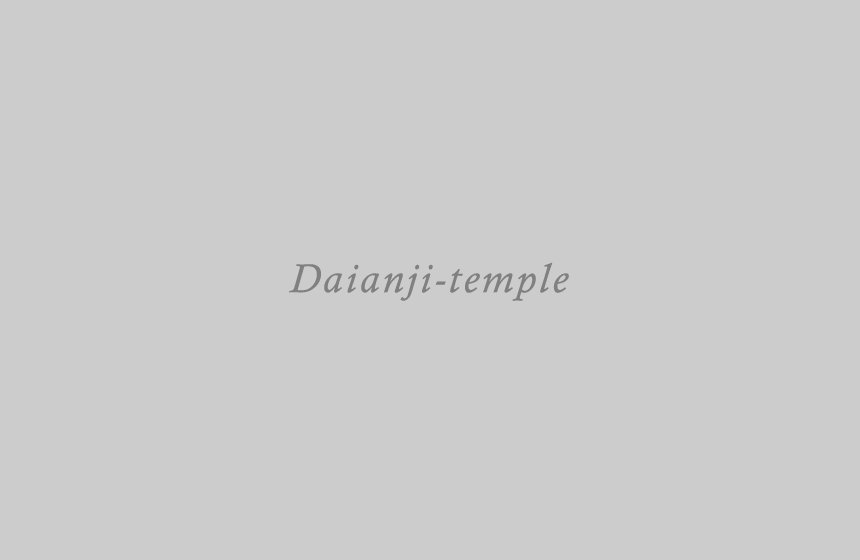
秋彼岸会九月彼岸七日間

開山忌(道慈律師・大般若経転読会)十一月二日
道慈律師は奈良時代を代表する高僧の一人で、大安寺の天平伽藍を完成させた人として知られます。
十六年間長安に学び 三論宗を伝えると共に先端の技術と文化を我が国にもたらしました。
また大般若経六百巻を転読して、国の安泰と人々の平安を祈る「大般若会」をおこし、 この法要は今日になお全国の寺々で盛んに行われています。
当山では、例年十一月二日、律師のご命日に大般若会を修し、大安寺創建の本義を顧み、律師の鴻恩を偲んで法要を営みます。毎年、律師への報恩謝徳と共に参詣各位のご平安と家内安全など御祈願いたしております。